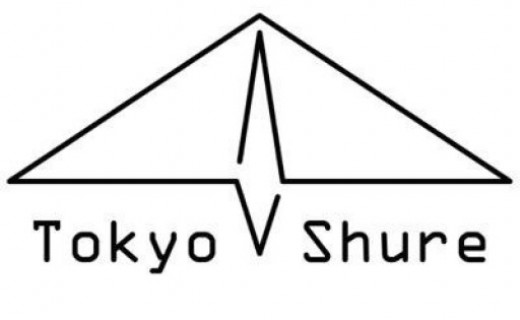1982年生 ● 新宿シューレ ● 新聞編集長 ● 不登校=13歳〜中2 ● シューレ在籍=中2〜20歳
不登校専門紙の発行 建前よりも共感できる事実が大事
私は現在、日本で唯一の不登校専門紙『Fonte』(旧不登校新聞)の編集長をさせてもらっています。毎月2回、読者は1900人。不登校経験を活かした仕事に就きたいと代表理事・奥地圭子さんに頼み込んだのが14年前。新聞づくり以外にも、全国各地から講演なども依頼され、とてもありがたい日常を送っています。
『Fonte』の特徴は、なんといっても不登校・ひきこもりをしている本人、経験者、親の生の声をたくさん載せていること。学校に行けない、働けない……、そんな状況のなかで本人や親が揺れに揺れまくっている本音を極力そのままのかたちで紙面化しています。
たとえば、わが子が不登校をしたとき「地面が割れたように感じた」と語るお母さんの話。「わが子はもう学校にあわない」と覚悟したものの、近所の子が校庭で遊ぶ姿を見て号泣したお父さんの話。「ふつうになりたい」と必死にがんばり続けた不登校経験者の話などなど。みなさんの本音に「すごく共感した」「やっと子どもの気持ちがわかった」という声をもらっています。
「目指したい姿」よりも、いまの率直な自分の気持ちから始める。建前よりも共感できる事実に出会えるほうが大事。これらの編集方針やメッセージは、私自身が東京シューレで感じてきたメッセージでした。
日常の出来事も楽しんだ
私が学校に行かなくなったのは13歳、中学2年生のとき。「いい学校へ行かなければ人生はない」と信じていました。しかし、中学校受験に失敗。挫折感や将来への不安感のなかで、私は歪んでいきました。そこに学校の理不尽さもあいまって「このままでは自分が自分でいられなくなる」と思い、学校を飛び出したのです。
その後、出会った東京シューレでは、いろんな経験をさせてもらいました。
94年、3か月の共同合宿を含むログハウス建設プロジェクト。97年の沖縄合宿、98年の児童福祉法改正に対する取り組み、99年の「不登校フェスティバル」には、「ねぷたをつくりたい」と提案し、実際に青森県にまで行きました。
そしてIDEC日本大会(00年)も欠かせない思い出です。このほか、日常的にも超高層ビルを非常階段だけを使って登ったり、「コロッケをみんなで100個食べる」という何の意味もないプロジェクトもやりました。でも、これらの眼に見える出来事よりも、日常のほうがより重要だと思っています。
気持ちを聞いてくれること 誰かが共感してくれること
私が初めて東京シューレに行った日、奥地さんが「シューレで何がしたいですか?」と聞いてきました。その一言にとっても驚きました。いままで掛け値なしに、気持ちを聞いてきた他人はいませんでした。特に学校ではそうです。
その日、見学を終えた後、シューレのなかで、ただただ2時間ほど世間話をして帰りました。この時間、とっても幸せな時間でした。何を話したのか、まったく覚えていませんが、将来とか、勉強とか、世間体とか、そんなものを何も気にする必要がない時間でした。
以後、たくさんの時間を世間話に費やしました。10代だったので見栄をはったりもしましたが、基本的には、共感しあったり、自分の失敗を笑いあったり、そんな時間をたくさん送りました。
最初の日に確かめられたことは「気持ちを聞いてくれる」こと、そして「誰かが共感してくれる」こと。この2つが以後、将来や勉強にそれでも揺れ続ける私を支えてくれました。
こうした日常や視線のなかで過ごしたことが「なにかやろう」という活力につながったことは、言うまでもありません。そして現在、今度は『Fonte』のなかで、自分が支えられてきたものをメッセージとして伝えていきたい。そう思いながら、今日も新聞づくりに取り組んでいます。